恵比寿駅前メンタルクリニック院長で一般社団法人リカレ協会 理事長 杉本あずさ先生と、片付けられない心理について意見交換させていただきました。
1. 片付けができない背景について
Q.「片付けができないことには様々な背景があると思いますが、それぞれ医療とカウンセリングの視点から、片付けに困難を感じる方に共通する要因はどのようなものがありますか?」

① 片付けや掃除という日常の作法(習慣)を親から学んでいない。代々受け継がれず(その親とその親というように)に育てられている場合もあります。
② 普段の生活が忙しすぎてルーティンワークに組み込まれていない(後回しになっている)
③ ゴミとして出すための仕分け方法が分からない(地域によってゴミの日に出す分別が難しい)朝早くの回収に間に合わない。
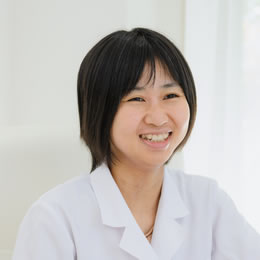
情報の整理や、要不要の判断、また実行力などの、片付けを行うのに必要な機能が十分に発揮できていない状態があると考えられます。
2.片付けとメンタルヘルスの関係性
Q.「片付けがうまくできないことが、精神的な健康にどのような影響を与えると考えますか? また、逆にメンタルの不調が片付けの難しさにつながることもありますか?」

①ストレスからの衝動買い
②片付けられないという自責の念→方法が分からない。モチベーションがすぐに下がってしまう
③不定愁訴など女性特有の体質の変化による体調不良が原因で何もできない。
④普段の生活が一変してしまうような出来事の影響による生活習慣の乱れから来るメンタルの崩壊
心と身体はつながっています(当たり前のようですが自覚がない人が多い)そして心の状態が部屋にも現れます。精神疾患が与える影響と認知能力の低下(加齢による)はとてもよく似ていて自分ではどうしょうもない状態になります。いままできちんと清潔に生きて来た人が加齢による認知症等で間反対な生活になってしまう場合もあります。
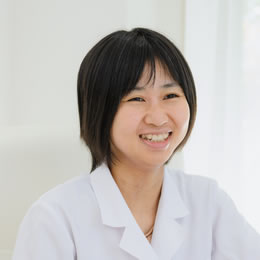
片づけられないことで、生活が混乱し、精神的ストレスとなるでしょう。また、抑うつ状態などのメンタルの不調は、片付けに必要な機能を発揮することを阻害し、片付けの難しさにつながることは良くみられることです。
3.片付けを支援する際のアプローチ
Q.「片付けの困難に対して、医療の現場ではどのようなサポートが可能でしょうか? 例えば、治療やカウンセリング、行動療法などの観点からアプローチすることはありますか?」

①家族が気づいて解決策として専門家(片付けやお掃除)に相談する。
②一日のタイムテーブルを作成することにより起きてから寝るまでの自分の行動を把握する。
③生活リズムや休息の取り方、十分な睡眠など片付けられるようになるまでメール等でフォローを継続。
④自分で管理できる「適量」が分かるまで仕分けを続けます。片付けは仕分けに始まり仕分けに終わりそれを継続することだと
自覚するまでくり返す必要があります。そのフォローとして定期的に訪問し連絡を取っています。
⑤粗大ごみに出せないような大きなモノは搬出や撤去処分までサポートしています。
⑥部屋のレイアウトが間違っている場合もあります。動線が確保できる暮らしやすいレイアウトをアドバイスします。
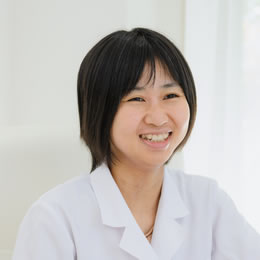
片付けを難しくしている精神的状態に関して、アセスメントや介入によるサポートが可能です。具体的には、原因を一緒に考えて、それに対してカウンセリングや投薬などの対応をしていくことが可能です。
4.メンタルヘルスの治療における薬の役割について
Q.現在、薬の役割に関しては、患者の状態により異なる理解があるかと思いますが、医療現場で「薬を卒業する」という目標が設定される場合や、実際に薬の減薬に向けて行うアプローチについて、詳しく教えていただけますと幸いです。

①クスリに頼りすぎずにクスリを使わないカウセリングも必要だと思います。
②規則正しい生活と運動と食べ物(添加物等)を変えることにより体質改善を図る為にも相談できる人を周りに作ることが大切だと思います。
③クスリを徐々に減らしていくことができる医師であってほしいと思います。
④精神疾患以外に他の疾患があるケースがあります。医師同士が連携して医療を考えることが大切だと思います。
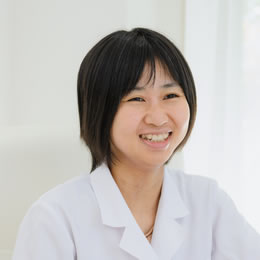
片付けを難しくしている精神的状態に関して、アセスメントや介入によるサポートが可能です。具体的には、原因を一緒に考えて、それに対してカウンセリングや投薬などの対応をしていくことが可能です。
5.片付け支援において、カウンセラーと医師が連携できることは?
Q.「片付け支援の現場において、カウンセラーと医師が協力できるポイントがあれば教えてください。」

①減薬するために心の状態と行動がどのように変化しているかを常に連携して見守る必要があると思います。
②時として治療目的ではなく隔離という形で入院する場合もあります。その時に心のケアのアプローチ方法を常に
進化させるためにも連携した勉強会などができたら良いと思います。
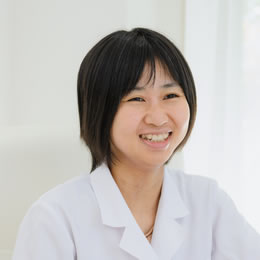
情報を共有し、役割分担をすることで、協力していきたいと思います。患者背景や治療状況などの情報を共有し、医師の治療とカウンセラーのカウンセリングで分担することが有効と考えます。当院では、医師とカウンセラーで情報共有を行なっておりますが、他機関になる場合では、必要時に手紙などでのやり取りをすることになります。
まとめ
今回、意見交換させていただいたのは、恵比寿駅前メンタルクリニック院長で一般社団法人リカレ協会 理事長 杉本あずさ先生です。(精神科・心療内科 オンライン診療 エ二キュア https://anycure.jp/)
治療やサポートは一方通行ではいけないと思います。
クスリをもらっていても大量に余らせているケースをよくみかけます。飲み忘れたり飲み切れずにいるのです。
片付けが苦手な人で発達障害などによる自己管理が難しい人も多いです。
近年、発達障害という名前が世に出て来るようになっても診断がつかないグレーゾーンの人、または診断がついたがゆえにリストラされる人もいます。
それによって鬱を発症する人もいます。診断がどこまで必要で診断後はどうケアしていく必要があるのか、その先のサポ―ト体制作りも
大切だと思います。
(片付けカウンセラー:中山ゆうみ)














